

| (1)地球温暖化問題と都市の考え方 | ||
|
*花木啓祐 (2003): 「都市の環境問題と地球環境問題」, in『都市を保全する』, 西村幸夫、大西隆、大垣眞一郎、岸井隆幸、小出和郎編, 鹿島出版会, 158-185. 一般的に言えば、都市の活動は温暖化の原因として大きく、またその対策が困難なのです。昔の公害のように、工場で対策をとって解決する問題ではありません。われわれの生活、社会自身がエネルギーや、製品に依存しているので、普通に生活しているだけで二酸化炭素を大量に出すことになるのです。 |
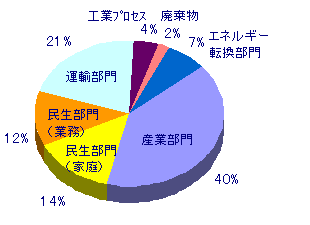 |
|
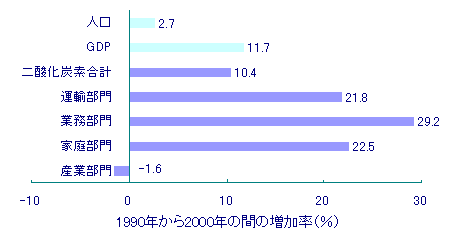 日本における部門別CO2排出量の動向 (1990年→2000年) |
しかし、下のグラフに見られるように、都市の単位で見ると、これらの部門の比率はさまざまです。ですから、二酸化炭素を減らす戦略も都市によって有効となる戦略が異なってくるのです。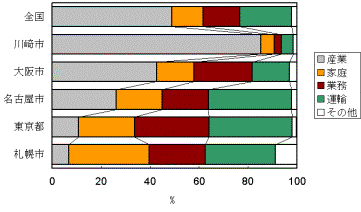 |
|
| (2)関連する研究活動 | ||
| 本研究室で行っている研究の多くは地球温暖化に関係しています。 このホームページ上でほかのテーマとして紹介しているものの中に関連するものも多くあります。ここでは、直接的に地球温暖化対策を研究テーマにしたもの、さらには、地域冷暖房の利用、未利用エネルギーの利用による二酸化炭素削減に関する研究について紹介します。 バイオマスや循環資源の活用、ゼロエミッションなど、温暖化対策に寄与する個々の技術やシステムについてはそれぞれの項を参照ください |
||
| 少子高齢化時代の到来に伴い、多くの余剰地が発生することが予想されます。二酸化炭素削減に向けて、そのような余剰地に太陽光パネルを導入してはどうでしょうか?発生する余剰地に全て太陽光パネルを敷き詰めたとしたら。。。多量の二酸化炭素削減が可能となります。しかし、一方で、そのような都市は実際に人々が居住するに適した都市となり得るでしょうか?景観は無機的で、人々の居住快適性が十分保たれないことが予想されます。 本研究では、そのような着想から、緑と太陽光を様々な割合で都市に導入した場合の、二酸化炭素削減量を算定し、その結果を用いて、住民に対し、どのような都市が望ましいかを、アンケート調査により解析しました。対象場所には下関市を選び、一対比較法により、人々の選好を抽出しました。 |
||
 |
 |
 |
| 大学は未来の社会の縮図です。キャンパスから発生する環境負荷の削減や地産地消、社会的な側面の改善など、キャンパスのサステイナビリティを高めるための活動が、イェール大学などアメリカを中心として多くの大学で展開されています。東京大学においても、持続可能なキャンパスを実現するために、教員、学生、職員が参加する「サステイナブルキャンパス」事業を推進しています。 我々の研究室では、キャンパスから排出される二酸化炭素削減に向けた施策の提案に関する研究を行っています。 |
||
| 地域冷暖房は、一定の地域内で冷房、暖房、給湯およびその他の熱需要を満たすため、一箇所または数箇所の熱供給プラントで製造された冷水、温水、蒸気などの熱媒を地域導管を用いて複数の熱需要家へ供給するシステムであり、個別供給では難しい、未利用エネルギーの活用に適しています。本研究では、日本全国に1400ある清掃工場からの廃熱を地域冷暖房に利用した場合の、二酸化炭素削減量の算定を行ないました。 |
||
| CDMは京都メカニズムの一つで、発展途上国で温室効果ガスを削減するプロジェクトを行って、そこで得る温室効果削減枠を売ることによってプロジェクトを成立させようとするものです。いま、日本のさまざまな会社がCDMに取り組んでいます。利益を得ながら温室効果ガスを減らせる、というのが特徴です。 都市を対象にしたCDMはさまざまなものが可能です。 ごみの埋め立て、交通、排水処理、など・・・ CDMはまだ実行段階に入ったばかりで大きな可能性を持っているといえるでしょう。 |
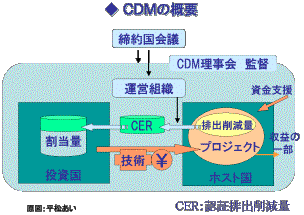 |
|